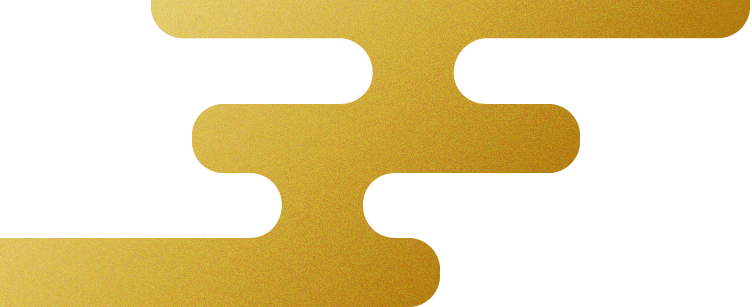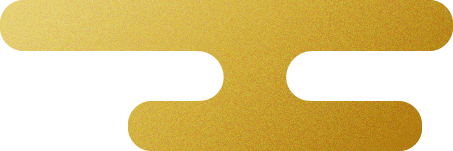【総集編】阿蘇にあるひのきが教えてくれた、“自然と共に生きる”ということ
2025年05月11日 07:00:00
南阿蘇に静かに佇んでいる
ご神木のDNAを受け継ぐひのきは、
ただの木ではありません。
それは自然、地域、文化、未来──
さまざまなものを静かに背負いながら生きる、
一本のメッセージツリー。
10回にわたる連載を通じて、
阿蘇の自然とひのきが持つ価値、
そして私たち自身ができる関わり方について
改めて見つめなおすことができました。
自然は“美しい風景”として一瞬や1コマで
終わるものではなく、
“共に未来をつくるパートナー”
になり得るのです。
第1回でご紹介した通り、
阿蘇の火山性土壌(リモナイト)は
通気性と保水性に富み、ミネラルを多く含むことから、
ひのきにとっては理想的な環境といえるでしょう。
まっすぐで美しい木目が育つのは、
こうした目に見えない
『大地の支え』があるからこそ。
第2回では、冷涼多雨な気候が
ひのきにとってストレスの少ない環境をつくり、
病気に強い健康な木を育てる要因
であることを紹介しました。
木の健康は、土地の健康から。
これは人間にも通じることです。
第3回では、挿し木という技術により
優良な遺伝子を忠実に受け継ぐ
南郷檜の稀少性にせまりました。
自然と人間の叡智(えいち)が織りなす
「命のバトンリレー」は、
持続可能なミライそのものです。
第4回では、阿蘇五岳と外輪山に守られた
南郷谷の地形が、ひのきの森にとって
まるで揺りかごのような存在であることを解説。
地形そのものが“天然の森林保全システム”なのです。
第5回では、地域文化と森林管理の融合を紹介。
森を守るのは専門家だけでなく、
そこに暮らす人々。地域ぐるみの関わりが
「森=みんなのもの」としての価値を育てています。
第6回・第7回では草原と野焼きに注目。
草原は水源を育み、森に安定した水を届け、
野焼きは草原の再生を促します。
火・水・土のサイクルこそが
阿蘇の自然を守っているという
循環のいわば原点が浮かび上がりました。
第8回では、南郷檜の木目の美しさと
建築材としての優秀さにフォーカス。
反りにくく香り高いその特徴は、
暮らしの質を静かに高めてくれます。
時を経て深まる質感は、
家族の歴史を共に刻む存在です。
第9回では、阿蘇の森林が
観光資源としても注目されている事実を紹介。
歩いて、香って、癒される
「体験型の自然」は、
記憶に残る旅の目的地として
新たな価値を持ち始めています。
そして最後の第10回では、
地域住民と共に
ミライに遺したい
理想の森をについて
お伝えしました。
子どもたちが植えた苗が、
ときには数十年後に家を支える柱となる──
そんな時間の循環に、
人と自然のあたたかな共創の意識が
息づいています。
たとえば、小学生たちが
「ひのきの植樹イベント」で学んだ体験。
木の香りに驚きながら、
自分たちが植えた苗木に手紙を書く。
「大きくなったら、また会おう」
それはミライに向けた
希望を込めた種まきです。
また、訪れた観光客が南郷檜の香りを
お土産として持ち帰るケースも増えています。
アロマオイルや小物などに込められた
香りや手触りは、日常にそっと
阿蘇の思い出を届けてくれるもの。
癒しだけでなく、暮らしへの誇りにもつながります。
野焼きを初めて手伝った人が
「火を扱うのに、こんなにも自然に
感謝したのは初めてだった」と語ったことも印象的でした。
その経験は、風景を守る“担い手”としての
意識を静かに芽生えさせてくれるのです。
南郷檜の森が育つ阿蘇には、
「自然と共に生きる」
という答えがあります。
それは派手な取り組みではなく、
小さな積み重ねの繰り返し。
草を刈ること、火を扱うこと、
苗木を植えること、木を使い切ること
すべてがミライにつながる森づくりです。
そして私たちも、
その一部になることが可能です。
日々の中でひのきに触れること。
自然のリズムを想像すること。
たとえささやかでも、
それは立派な「森づくり」の一歩。
南郷檜というひのきが、
100年後も阿蘇の空の下に立ち続けるように。
私たちもまた、日々の暮らしの中に
自然と寄り添う選択を重ねていけたら──
それが、この森の物語を、
次の世代につなげる
“根”になるのではないでしょうか。
6月24日夜20時からオンラインセミナーに登壇
ご神木のDNAを受け継ぐ
100年ひのきについて語ります
この檜(ひのき)を手にして
人生を変えた方々も紹介しますよ。
ご神木のDNAを受け継ぐひのきは、
ただの木ではありません。
それは自然、地域、文化、未来──
さまざまなものを静かに背負いながら生きる、
一本のメッセージツリー。
10回にわたる連載を通じて、
阿蘇の自然とひのきが持つ価値、
そして私たち自身ができる関わり方について
改めて見つめなおすことができました。
自然は“美しい風景”として一瞬や1コマで
終わるものではなく、
“共に未来をつくるパートナー”
になり得るのです。
第1回でご紹介した通り、
阿蘇の火山性土壌(リモナイト)は
通気性と保水性に富み、ミネラルを多く含むことから、
ひのきにとっては理想的な環境といえるでしょう。
まっすぐで美しい木目が育つのは、
こうした目に見えない
『大地の支え』があるからこそ。
第2回では、冷涼多雨な気候が
ひのきにとってストレスの少ない環境をつくり、
病気に強い健康な木を育てる要因
であることを紹介しました。
木の健康は、土地の健康から。
これは人間にも通じることです。
第3回では、挿し木という技術により
優良な遺伝子を忠実に受け継ぐ
南郷檜の稀少性にせまりました。
自然と人間の叡智(えいち)が織りなす
「命のバトンリレー」は、
持続可能なミライそのものです。
第4回では、阿蘇五岳と外輪山に守られた
南郷谷の地形が、ひのきの森にとって
まるで揺りかごのような存在であることを解説。
地形そのものが“天然の森林保全システム”なのです。
第5回では、地域文化と森林管理の融合を紹介。
森を守るのは専門家だけでなく、
そこに暮らす人々。地域ぐるみの関わりが
「森=みんなのもの」としての価値を育てています。
第6回・第7回では草原と野焼きに注目。
草原は水源を育み、森に安定した水を届け、
野焼きは草原の再生を促します。
火・水・土のサイクルこそが
阿蘇の自然を守っているという
循環のいわば原点が浮かび上がりました。
第8回では、南郷檜の木目の美しさと
建築材としての優秀さにフォーカス。
反りにくく香り高いその特徴は、
暮らしの質を静かに高めてくれます。
時を経て深まる質感は、
家族の歴史を共に刻む存在です。
第9回では、阿蘇の森林が
観光資源としても注目されている事実を紹介。
歩いて、香って、癒される
「体験型の自然」は、
記憶に残る旅の目的地として
新たな価値を持ち始めています。
そして最後の第10回では、
地域住民と共に
ミライに遺したい
理想の森をについて
お伝えしました。
子どもたちが植えた苗が、
ときには数十年後に家を支える柱となる──
そんな時間の循環に、
人と自然のあたたかな共創の意識が
息づいています。
たとえば、小学生たちが
「ひのきの植樹イベント」で学んだ体験。
木の香りに驚きながら、
自分たちが植えた苗木に手紙を書く。
「大きくなったら、また会おう」
それはミライに向けた
希望を込めた種まきです。
また、訪れた観光客が南郷檜の香りを
お土産として持ち帰るケースも増えています。
アロマオイルや小物などに込められた
香りや手触りは、日常にそっと
阿蘇の思い出を届けてくれるもの。
癒しだけでなく、暮らしへの誇りにもつながります。
野焼きを初めて手伝った人が
「火を扱うのに、こんなにも自然に
感謝したのは初めてだった」と語ったことも印象的でした。
その経験は、風景を守る“担い手”としての
意識を静かに芽生えさせてくれるのです。
南郷檜の森が育つ阿蘇には、
「自然と共に生きる」
という答えがあります。
それは派手な取り組みではなく、
小さな積み重ねの繰り返し。
草を刈ること、火を扱うこと、
苗木を植えること、木を使い切ること
すべてがミライにつながる森づくりです。
そして私たちも、
その一部になることが可能です。
日々の中でひのきに触れること。
自然のリズムを想像すること。
たとえささやかでも、
それは立派な「森づくり」の一歩。
南郷檜というひのきが、
100年後も阿蘇の空の下に立ち続けるように。
私たちもまた、日々の暮らしの中に
自然と寄り添う選択を重ねていけたら──
それが、この森の物語を、
次の世代につなげる
“根”になるのではないでしょうか。
6月24日夜20時からオンラインセミナーに登壇
ご神木のDNAを受け継ぐ
100年ひのきについて語ります
この檜(ひのき)を手にして
人生を変えた方々も紹介しますよ。

↑人生激変したSNSインフルエンサーみやはらゆきこさん
セミナーの告知は
メルマガ登録にてご案内しております
ご登録はこちら↓
神様が自然とやってくる台所メルマガ
ご登録特典として九州産ひのきで作られたチップをプレゼントしてます
※手前にある商品を郵送
セミナーの告知は
メルマガ登録にてご案内しております
ご登録はこちら↓
神様が自然とやってくる台所メルマガ
ご登録特典として九州産ひのきで作られたチップをプレゼントしてます
※手前にある商品を郵送

※ご住所などの連絡先をを入力された方のみ